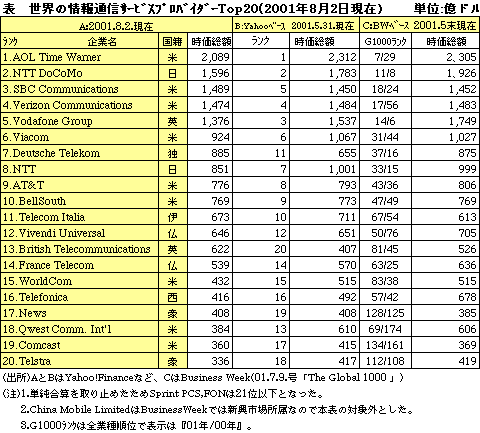トップページ > レポート > マンスリーフォーカス > 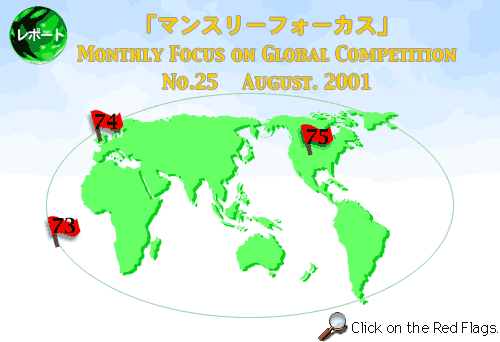
世界の通信企業の戦略提携図(2001年8月6日現在) |
73.AT&Tブロードバンドの行方コムキャストの買収提案とAOL TWとの統合協議 上位合併の意義は、(1)AT&T Br+Comcastの加入数はTW加入数のほぼ2倍という規模の利益、もちろんAT&T+TWの規模はさらに大きい、(2)厳しい規制の結果米国のCATV システムは地理的にバラバラなのが、隣接システムの合併で固定費用やマーケティングコストを下げることができる、(3)合併で全米トップ10都市のうち8市で優勢となり、CATVが始めて全国ネットの地位を得て広告力を増すなどである。当然独禁の観点からチェックは厳しいが、ブロードバンド競争はディジタルCATV、光ケーブル/ADSL、無線系(2.5G/3G、WLL)と三つ巴ないし五者間なので、CATV規制は現行よりも厳しくなることはないとの見方が一般的である。 AT&Tは、既報の通り(マンスリー2000年11月「No.47 AT&T4分割の意味するもの」参照)、企業用長距離通信のAT&T Business、住宅用長距離通信のAT&T Consumer、携帯電話のAT&T Wireless、CATVのAT&T Brに分割する再編成計画を発表し、2001年7月9日にはAT&T Wirelessを独立(AT&Tが株主にAT&T Wirelessの普通株を交付し、資本関係を分離) させた。再編成計画では、AT&Tは2001年内AT&T Brについてトラッキング・ストック(部門収益連動株)を発行し、2002年に分離独立させることとしていた。 Comcastの提案は、Comcastが445億ドル相当の自社株を発行してAT&T株主に交付する株式交換によりCATV加入数2,200万の合併企業(AT&T株主の保有率51%)を創設し同時にAT&T債務135億ドルを引き受けるもので、現在収益力がComcastの半分しかないAT&T株主が高収益株を手にするので、AT&T株主は得だとする。 Comcastが8月2日に発表した2001年第2四半期業績は、連結収入前年同期比20%増の23億ドル、利益が前年同期の1.877億ドルより下がって3,520万ドルになったが、株価は8月1日の終値38.05ドルより6セント上昇し、アナリストもComcastはこのIT不況期に連続して好業績を上げている始めてのディジタル化CATVだと高く評価している。 AT&T Brを争うComcastの対抗馬はAOL TWのほかに、MSO第5位のコックス・コミュニケーションズ(Cox、600万加入)やウォルトディズニー(WD)も候補と見られるが、既報の通り(マンスリー2000年12月No.50「AT&Tはリバティー・メディアを手放す方向」参照)、近くAT&Tから分離される予定のリバティー・メディア・グループ(Liberty Media: LMG)が最も注目されている。AT&Tに買収されたTCIのCEOでAT&T取締役兼LMG会長のJ.マローンが今もLMGの個人筆頭株主であり、LMG独立後退任予定の取締役をいち早く7月10日に退いたこと、LMGがドイツテレコム(DT)からCATVシステムを買収し、従来からの英国テレウェストの25%持株などを合わせると今や欧州一のCATVオペレーターになりつつあるため、早晩マローンがAT&T Br買収を提案すると見られるのである。 AT&TはComcast提案は低すぎると値段付けが上がるの待つ姿勢で、いずれ高値の買い手と成約するだろう。しかし、株価引き上げを狙った4分割は買収され易いユニットをつくり出したわけで、株価が上がって過去の投資は回収できAT&Tブランドを共用する各「AT&Tユニット」が栄える日が来てもメガキャリアーAT&Tは消えるわけであって、株主は満足しても企業体の成長源を失うM&Aは後味の悪いものである。 IT不況期における情報通信企業の浮沈 民間設備投資低下の理由は、昨秋以来の景気減速で重要が落ち込んで在庫が大幅に増え、このところ発表が続いた2001年第2四半期(4-6月期)中間決算で減益傾向が支配的、株価が急激に下がっているからである。特に情報技術(IT)ブーム時の過剰投資の反動が問題で、90年代後半に年率二桁の伸びを続けてきた機器・ソフトウエア投資が2000年後半から失速し、2001年4-6月期投資の減少率は19年振りの大きさだった。1998-99年2年間の伸び率は、かつてインテルの創始者G.ムーアが唱えた「半導体の処理能力は1年半ごとの倍増する」とのムーアの法則があてはまる勢いだったが、今や逆サイドで半減が累乗する収縮振りである。 半導体・集積回路はほぼ全産業の基盤だが、電子部品、電子応用機器、コンピュータ、通信機器、光機器などのIT産業で高度利用が多く、家電(消費者製品・サービス)産業やテレコム産業でもディジタル化、マルチメディア化またモバイル.コンピューティング指向に伴いICが複雑化した分野ほど『マイナス・ムーア』の影響が大きい。米国産業の現状では、まずハードウエア・メーカーが不調で、特に携帯電話の大量在庫を抱えた通信機器メーカーが最大の落ち込みを示し、電子部品メーカーはまだましでソフトウエア業者も影響を受け始めた情勢である。 ビジネスウィーク(BW)誌2001年7月9日号の「2001年版世界のトップ企業1000社」は、トップ10からインテル、シスコ・システムズ、ノキア、ボーダフォン・グループ、NTTドコモなどハイテク企業(ニュー・エコノミー)が落ち、代わりにファイザー(Pfizer、薬品)、AOL TW(消費者サービス)、シティ・グループ(金融)、シェルとBPアモコ(エネルギー)などの在来型産業(オールド・エコノミー)が入ったと伝え、ハイテク企業一番の落ち込みはルーセント・テクノロジー(No.17→No.182)と紹介している。 IT不況期における情報通信企業の浮沈をBusiness Week誌ランク(2001年5月末現在)とフォローアップとしてのYahoo Financeベースランク(2001年8月2日現在)を合成した次ぎの表で紹介する。 「表 世界の情報通信サービスプロバイダーTOP20(2001年8月2日現在)
まず同一企業の時価総額がベースにより少なからず異なる場合があることに気付く。NTT DoCoMoはニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場されてないため推定値によっているから当然だが、例えばドイツ・テレコムのようにNYSEの原株価を同じで時価総額がひどく違うのは、何故か知りたいものである。今や公開市場で株価が時時刻々変わり、四半期業績は国際会計標準で算定され迅速に公表される時代に、キャッシュフロー経営上の企業価値があいまいに算定されていては問題があろう。なお、今回の表は7月31日現在で作成したかったが、「コード・レッド」ヴィールス対策のためかYahoo Finance数値が'7月31日と8月1日に更新されなかったので8月2日現在とした。また、情報通信企業の選定対象は、BW誌分類における50 Telecommunications Services、25 Consume/D(但しサービス中心のもの)とし、45 Information Technologyは除くなど従来のものを改めた。 表のC項「G1000ランク」に見る通り、AOL TWが合併実施の結果2000年の第29位から2001年の第7位に跳ね上がり、SBC Comm. (No.24→No.18)、Verizon Comm.(No.56→No.17)、BellSouth(No.49→No.47)、Vivendi Universal(No.76→No.50)、Qwest Communications Int.(No.174→No.69)、Comcast(No.161→No.134)がそれぞれがランクアップしたほかは、みな下がっている。ベル系地方持株会社が4社とも上がっているが、Qwestは合併効果、Verizonのジャンプは合理化努力を投資家が評価したものである。 Deutche Telekom、France TeleDcom、British Telecomの西欧3大キャリアーが大きく下がったのは、それぞれ6月末でDTは583億ドル、BTは241億ドル、FTは2000年末で570億ドルの負債があるためと思われる。 |
74.双方向ディジタル放送の可能性ー英国の経験英国のCATV事業はテレウェスト(Telewest)とNTLの寡占になっていたところ、2000年1月には109.10ドル、2001年初頭で1株44.5ドルだったNTLの株価がこの7月19日に4.75ドルに下がった。2001年第2四半期業績発表を繰り上げる予定がもれて急落したことは、純負債156億ドルに及ぶNTLの苦境と落ち着かない投資家の心境を表している。7月26日に発表されたEBITDA(利払い・課税・償却前利益)は1.15億ドルで、2001年の年間利益見通しは4.85億ドル、さらに2002年と2003年の営業利益はそれぞれ9.5億ドル、15.75億ドルという好業績見通しを示した。 NTLは苦境を乗り切るのにフランステレコム(FT)の力に頼っている。2000年2月にスイスのペイTV会社Cablecomを買収するとき資金援助して20%株主になったFTが出資を引き上げることができるか、その資金ぐりが注目される。 Telewestも経営的に快調ではないが、筆頭株主はマイクロソフト(MS)、リバティ・メディア(LMG)、メディアワン(MediaOne)合計50.1%の外資である。 NTLとTelewest合わせて有料ディジタルTV加入数は160万に達したが、積極経営は外資に支えられている面が強い。BBCを堅持しつつ民間放送は“ウィンブルドン方式”で発展してきた英国メディア業界の典型と言える。 衛星放送は1989年2月にルクセンブルグのアストラ衛星によるマードックのベンチャーSkyTVで始まった。国内衛星放送のBSBが1990年4月サービス開始で追い掛けたが直ぐに行き詰まり、SkyTVに買収されて同年11月にBSkyBとなった。BSkyBはアナログ放送では圧倒的な強さを示したが、1998年10月開始のディジタル放送Sky Digitalは無料STB(セット・トップ・ボックス)による販売合戦出費のため赤字続きで、BSkyBも2001年6月までの年次決算で前年度比倍増赤字7.38億ドルを記録した。Sky Digitalの主要株主はBskyB-News Corp40%、Vivendi Universal24%で、有料加入数は現在550万である。 地上波ディジタル放送は、民放への周波数帯割り当てに際しBSyB出資会社を退け、地域番組会社大手カールトンとグラナダ合弁のONdigitalに免許を与え1998年11月に開始した。ONdigitalは2000年3月末に加入世帯数110万に達したところで、歴史ある民放名を取り込んだ社名ITV Digitalに改称した、ディジタルTVはDigital CATV、SkyDigital、ITV Digital合計で1000万加入に近付き一応成功したが、普及率は2,500万世帯の40%に過ぎない。双方向ディジタルサービス革命が起きたとはまだ言えない。 双方向TVのもう一つ電話系のADSL/光ケーブルについては、BTは放送系とシェア争いを展開するよりゲームの試行サービスを提供するなど新サービス指向で、コスト高からADSLの家庭普及は緩慢にしている。企業通信指向のディジタル統合サービス事業オープンワールド(BTOpenworld)は、7月31日に中小企業・SOHO向け双方向衛星サービスを11月に地域拡大すると発表した。一方、米国のバブコック・アンド・ブラウン以下の金融コンソーシアムによるBT加入者網115億ドル買収提案のやり取りが続いている。 |
75.衛星通信新時代と新イリジウムの経営戦略今なお国際通信の半分は衛星経由 インテルサットの民営化については、基本計画が第24回締約国総会(1999年10月)で承認された後、基本的事項を詰める段階で既報(マンスリー2000年4月「No.25国際通信組織の改革問題」参照)のようなトラブルがあったものの、最終的計画は第25回締約国総会(2000年11月)で確定していた。計画の主要点は(1)持株会社(Intelsat Ltd)をバミューダに設置する、(2)米国籍の衛星免許保有会社(Intelsat LLC)を設置する、(3)サービス会社(社名未定)を米国に設置する、の4点からなり、今回がその第一着手である。 ただ第一着手と言っても、放送番組中継やインターネット向け専用線という競争性の強い事業は既に先行して1998年に分離子会社ニュースカイ(New Skies Satellites NV)が設立されており、今回も1999年12月に設立されたサービス会社Intelsat Ltdへの資産譲渡が、計画期限の2001年7月18日19時59分59秒に行われたものである。衛星免許保有会社Intelsat LLCも2000年1月に設立され、運用免許を受けている。 問題は資本金で、145締約国の約200事業者から出資された18億ドルの資産を承継したIntelsat Ltdは2002年早期に一部(20~30%)を上場する計画で、時価総額30億ドル以上を期待しているが市場評価は幾らになるのか注目される。 国際機関として最終のインテルサット2000年決算は売上高11 億ドル、利益5.04億ドル、EBITDA86%という好成績を記録した。 調査会社TeleGeographyの「国際帯域(International Bndwidth 2001、01年4月刊行)」によれば、先進国の発達した地上ルートの帯域売買価格が1998年から2000年に年率50%で下がったのに、SES AstraとGEアメリコムは税引き前利益率80%を維持してきた。静止型衛星による2点間国際通信サービスは、電話やIP基幹網については光ファイバ通信に対し競争力を失っているが、放送や途上国のISP基幹接続という面的サービスでは衛星通信にまだ力がある。実際ニュースカイ利用IPトラフィックの成長率は1999年の7%から2000年の25%に伸びている。光ファイバはDWDM(高密度波長多重)で通信事業者に無限の帯域を提供するが適用領域が限られており、衛星は帯域が限られるが適用領域は無限である。全通信を光ファイバ化できないからには、当分の間国際通信で衛星通信は使い続けられ、国際通信網では衛星と光ケーブルが相互補完的役割を果たしていくだろう。 新イリジウムの経営戦略 1998年10月にサービス開始した旧イリジウム社(Iridium LC)は50億ドル投資して、1分8ドルの通話サービスを100万加入提供で単年度収支均衡、10年かけて最低3,200万加入に提供することを目標に、立ち上がり6カ月で50万加入集めるため1.8億ドルの広告を打ったが、15,000加入を集めただけで開業9カ月後に倒産した。 2000年末に低軌道衛星66個システムを2,500万ドルで入手した新イリジウム社(Iridium Satellite LLC)は、インフラコストが大安で負債もないことから経営モデルを変え、通話料を1分1.5ドルに下げ、2003年半ばまでに65,000加入集めれば単年度収支が均衡する計算で、国防(平和維持部隊PKF)や石油・天然ガス探査というニッチ市場狙い戦略をとり、まず米国国防総省から利用者2,000名1カ月300万ドルまでの使用契約を獲得し、システム運転コストの40%を確保した。旧イリジウム社は一般の携帯電話より重くて高値の移動電話を売ろうとしたが、新イリジウム社は現用可搬型衛星電話より小さくて安いオルタナティブを売ることにしたのである。 また旧イリジウムは電話サービスだけだったが、新イリジウムは2001年6月から低速ではあるが世界中どこででもインターネットにアクセスできるサービスを開始し、テキスト・メッセージング・サービスを加えた。衛星ベースのデータ/テキスト・サービスは電力障害や天災地変に強いので需要が期待される。 旧イリジウムは欠陥ある市場予測に基づく膨大な投資に伴う借金で潰れたが、新イリジウムの経営戦略はその教訓を生かしたことで賢明なやり方に見える。議論の多い次世代(3G)携帯電話戦略に、この教訓はどのように生かされるだろうか。 |
| 寄稿 高橋洋文(元関西大学教授) nl@icr.co.jp(編集室宛) 入稿:2001.8 |
| このページの最初へ |
| InfoComニューズレター[トップページ] |